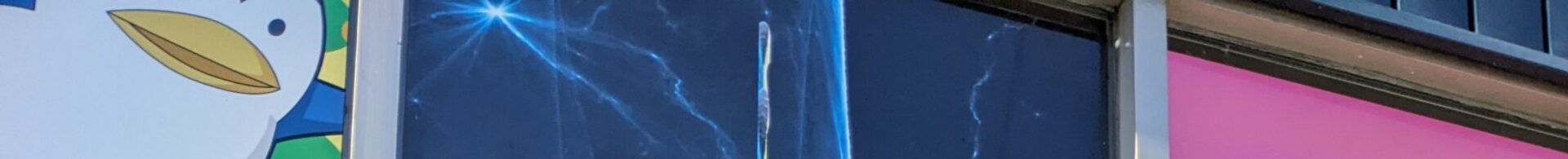クマ被害の深刻化と「捕殺」対策の限界
※本ページはプロモーションが含まれています
近年、日本各地では野生クマの出没が急増し、地域社会や生活に深刻な影響が生じています。2025年にはクマによる人身被害で、過去最多となる13人の死亡が確認されており、被害例は北海道や東北地方など広範なエリアで発生しています。これを受けて、自然保護団体「日本熊森協会」は、環境省に対し捕殺一辺倒の対策を見直すよう緊急要請を行いました。
クマ出没地域では、地域イベントの中止や保育園・学校の送迎強化など、住民の生活や経済活動にも大きな影響が出ているのが現状です。政府も対策の強化を進めていますが、その中心は「捕殺(クマの駆除)」による即時的な安全確保策です。しかし、これだけでは根本的な解決には至らないとして、各方面から対策見直しを求める声が高まっています。
## 日本熊森協会が訴える「長期的視野」とは
日本熊森協会は2025年11月6日、東京都内で記者会見を開き、環境大臣と農林水産大臣宛てに「緊急要請書」を提出したことを発表しました。要請書の主旨は、捕殺一辺倒の対策では限界があり、地域全体で被害防除や森林再生など長期的な視野に基づく多角的な取り組みが必要だという点です。
同協会会長の室谷悠子氏や北海道・秋田・岩手・宮城・福島の支部長たちは、「毎日のようにクマによる事故が報道されており、被害防止のため本気で取り組みたい」と理解を求めました。単にクマを排除するのではなく、人とクマが共に生きていける社会に戻すため、森と人との距離の確保、自然環境の回復、餌場管理など抜本対策の推進が強調されています。
## 政府の現行方針と課題点
2025年10月30日に開催された政府関係閣僚会議では、人里に出没したクマを迅速に駆除できるよう緊急猟銃を実施できる者の拡大措置など、捕殺を中心とした対策が議論されました。しかしこうした方針に対し、「捕殺だけでは問題が根本的に解決しない」と日本熊森協会は警鐘を鳴らしています。
現行の捕殺対策は、目の前の被害防止に即効性がある一方で、根本原因の解決に繋がらないことや、適切な生態系管理や人間と動物の共存という視点が希薄化するリスクも指摘されています。また、過剰な捕殺は生態系バランスの崩壊や将来の自然・農業への悪影響も招きかねません。
## 今後求められる包括的なクマ対策
今後のクマ被害対策には、短期的視点だけでなく中長期的な施策の強化が不可欠です。日本熊森協会が提言するのは、以下のような「社会全体で取り組む包括的な対策」です。
– 森と人の距離の確保や餌場対策の徹底
– 山林の復元、生態系の回復事業への積極的な投資
– 農作物被害防除や地域ぐるみの監視・通報体制の強化
– 子グマや個体ごとに対応を見極めた管理策の確立
また、教育や広報活動を通じて「クマだから殺してよい」という風潮を改め、人とクマが持続可能に共生できる環境づくりへの意識改革も重要となります。
***
このように、単なる捕殺強化策だけでなく、被害防除・森の再生・共生社会の構築といった複数の視点から、抜本的にクマ対策を進化させる必要性が高まっています。