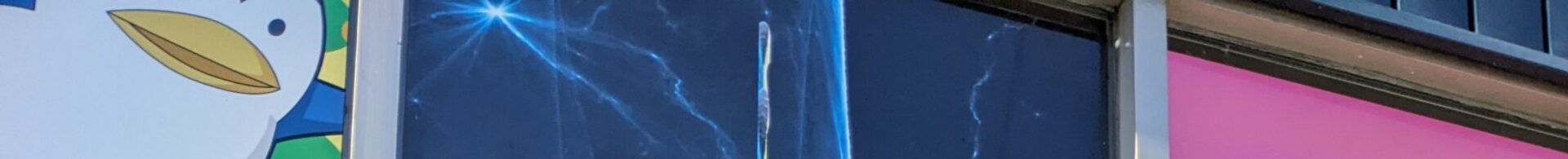死人に名誉毀損罪は成立しないのに、立花孝志氏は逮捕されたのか──警察が動いた「被害の構造」を読み解く
※本ページはプロモーションが含まれています※
■ 立花孝志氏、名誉毀損容疑で逮捕という衝撃
2025年11月9日、政治団体「NHKから国民を守る党(現・政治家女子48党)」の党首・立花孝志容疑者が、元兵庫県議に対する名誉毀損容疑で兵庫県警に逮捕された。報道によれば、立花氏はすでに亡くなっている元県議について、YouTubeなどの動画配信やSNS上で「虚偽の情報を発信した疑い」が持たれているという。
だがここで誰もが首をかしげた。
「死人に対する名誉毀損罪は、そもそも成立しないはずでは?」
そう、刑法230条で定める名誉毀損罪の保護法益は「生きた人の社会的評価」。死者本人は権利主体ではないため、教科書的には**『死人に対する名誉毀損は処罰されない』**とされている。
それなのになぜ、警察は逮捕という強い措置を取ったのか?
この「なぜ」を掘り下げると、現代社会における名誉・表現・ネット拡散の三重構造が見えてくる。
■ 原則:死者の名誉は刑法上保護されない
まずは基本の確認から。
刑法230条はこう定めている。
「公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。」
ここでいう「人」とは、生存している自然人を指す。
最高裁も一貫して「死亡した者に対する名誉毀損罪は成立しない」としており、判例・通説も一致している。なぜなら、死者はもはや社会的評価の主体ではなく、刑事法で保護すべき「名誉権」そのものが消滅しているからだ。
したがって、もし「亡くなった○○氏は不正をしていた」と発言したとしても、それが虚偽であっても刑法上は死者本人への名誉毀損とはならない──これが原則的な理解である。
しかし、ここに一つの「穴」がある。
死者の名誉を傷つける行為が、遺族や関係者の人格権を侵害する場合には、別の角度から刑事・民事責任が問われうるのだ。
■ 例外:遺族の「敬愛追慕の情」が侵害された場合
法学では、死者の名誉に関して「遺族の敬愛追慕の情(けいあいついぼのじょう)」を保護すべき利益として認める考え方がある。
これは、死者本人を守るのではなく、遺族の精神的平穏や人格的利益を守る枠組みだ。
過去にも、芸能人や政治家などが亡くなった後に「虚偽の報道」や「悪意ある中傷」が行われた場合、遺族が民事上の損害賠償請求を起こし、裁判所が「遺族の人格的利益侵害」として賠償を認めた例がある。
今回の逮捕も、この延長線上にある可能性が高い。
つまり、警察は「死者本人ではなく、遺族の名誉や感情が侵害された」と見たのだ。
■ 逮捕に踏み切った「3つの理由」
警察が本件であえて逮捕という強い措置に踏み切った背景には、次の三つの要素があると考えられる。
① SNSや動画による「公然性と拡散性」
立花氏は長年、YouTubeなどで政治・社会問題を発信し続けてきた。チャンネル登録者は数十万人規模にのぼり、発言には大きな影響力がある。
この影響力のもとで、虚偽の内容を繰り返し発信した場合、社会的信用の失墜が一気に拡散する。
しかも一度ネットに流れた情報は、削除しても完全には消えない。
警察としては、被害が拡大・永続化する危険性を重く見た可能性が高い。
② 「虚偽の事実摘示」だった
刑法上の名誉毀損罪が成立するのは、意見や論評ではなく、具体的な事実を摘示した場合である。
「彼は不正をした」「裏金を受け取った」などの断定的発言は、「事実の摘示」にあたる。
これが虚偽だった場合、真実性・相当性の立証ができなければ有罪の可能性が生じる。
報道によれば、立花氏が配信した内容には、すでに死亡している元県議に対して「犯罪行為をした」などの表現が含まれていたという。
つまり単なる政治的意見ではなく、事実に関する断定的な発言だったことが警察の判断を後押しした。
③ 遺族への実害・被害届の存在
捜査当局が動くには、告訴や被害届が必要だ。
今回、元県議の遺族や関係者が「名誉を汚された」として正式に訴え出たことが報道からうかがえる。
もし遺族が「虚偽の情報で家族の名誉が踏みにじられ、社会的被害を受けた」と主張すれば、警察はその精神的苦痛を「名誉毀損の構成要件に準ずる被害」として捉えることができる。
刑法上の名誉毀損に直接は当たらなくても、被害の実態と社会的悪質性があれば、逮捕という手段を取ることは法的に説明がつく。
■ 「表現の自由」と「名誉保護」のせめぎ合い
ここで忘れてはならないのが、立花氏の発言には「政治的発言」「告発的性格」があった点だ。
日本国憲法21条が保障する表現の自由は、民主主義の根幹にかかわる。
政治家が不正を指摘することや、行政を批判すること自体は当然自由である。
しかし、その自由は無制限ではない。
最高裁判所も、「公共の利害に関する事実であっても、真実性または真実と信じる相当の理由がなければ違法となる」と繰り返し判示している。
つまり、立花氏側が「公益のための告発だった」と主張しても、根拠の薄い断定や虚偽の拡散であれば、表現の自由の範囲を逸脱する。
SNS社会では、この線引きがますます難しくなっている。
発信者が「正義感」で投稿しても、根拠のない情報を流せば「事実を捏造した名誉毀損」と見なされることがある。
立花氏の今回の逮捕は、その境界線をめぐる象徴的な事件といえる。
■ 「被害の構造」──亡き人を介した二次被害の連鎖
この事件を単なる「法解釈問題」として片づけると、見誤る。
焦点は、「死者に対する発言」が引き起こす生者の苦痛だ。
- 亡くなった家族が、ネット上で「犯罪者」「裏切り者」と断定的に言われる。
- 真偽不明の噂がSNSで再拡散され、子どもや配偶者が誹謗中傷を受ける。
- 名誉回復を訴えても、ネット記事や動画が半永久的に残る。
このように、死者を中傷する行為は、遺族を二次被害者に変える。
警察が動いた背景には、こうした被害の深刻さがある。
法的には「死者本人は保護されない」が、現実には「遺族が社会的・精神的損害を受けている」。
ここに、警察が重視した「被害の構造」があると考えられる。
■ 今後の焦点:検察の判断と裁判所の見解
今後の焦点は、検察がどのように立件するかだ。
もし起訴されれば、次の点が争点になるだろう。
- 摘示された事実が虚偽だったかどうか
- 真実と信じるに足る相当な理由があったか
- 遺族の人格的利益をどの程度侵害したか
- 発言の公共性・公益性の有無
これらをどう評価するかによって、
- 「刑法230条の拡張解釈(遺族名誉毀損型)」
- 「別条文による人格権侵害」
などの法理構成が議論されるだろう。
もし裁判所が「死者への中傷が遺族への侵害として刑事的にも保護されうる」と判断すれば、これは日本の刑事法実務に新しい一線を引く判決になる可能性がある。
■ 結論:これは「表現の自由の事件」ではなく、「被害の可視化」の事件だ
立花氏の逮捕は、単に一人の政治家の問題ではない。
SNS社会において、「亡くなった人をネタに語る」ことがいかに遺族を傷つけるか、
その「被害の可視化」を示した事件である。
警察が動いた理由は、
「死者の名誉を守るため」ではなく、
「残された人々を守るため」だった。
ネットで発言する誰もが、いま一度この構造を意識すべきだ。
生者の言葉は、死者を介して、なお生者を傷つける。
そして、そこに法の介入が必要と判断された時代に、私たちは立ち会っているのだ。